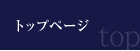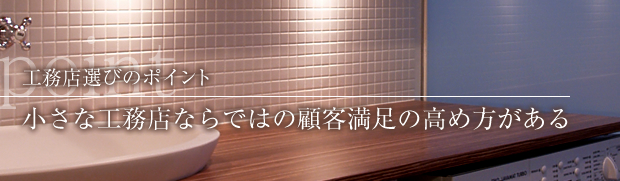
 現在大内さんがコンタクトをとるOB顧客はおよそ250組。「もともと口下手で、営業をする性ではない」という大内さん。新規客への営業は行わず、OB施主とのつながりを大切にし、そこからのリピートや紹介でリフォーム受注をとる。
現在大内さんがコンタクトをとるOB顧客はおよそ250組。「もともと口下手で、営業をする性ではない」という大内さん。新規客への営業は行わず、OB施主とのつながりを大切にし、そこからのリピートや紹介でリフォーム受注をとる。
大内さんの実践はあくまで基本に忠実だ。
まず設計事務所の設計物件でも引渡し後3カ月、6カ月、1年の定期点検を行う。建具の建て付けや飾りの一枚棚の取り付けなど、大内さんがその場でできる仕事は基本的に無償で行う。
日頃のケアとして、「お客様から電話を頂いたときはその日か翌日にうかがう」という基本姿勢を守る。さらに「新しい現場が決まると、すぐに近くのOB顧客の顔が思い浮かぶ」という大内さんは、現場を訪れる際には時間をみつけてOB顧客宅に立ち寄る。OB顧客全員に毎年配布する自社カレンダーも、できる限り顧客宅を訪ね手渡しで届けることも怠らない。「地道な努力を積み重ねることで、いざというときに顔を思い出してもらえる」(大内さん)
ただし、こうしたアフターケアより重要な事として大内さんは「完成住宅の満足度を高めること」を挙げる。「施主に対しても、施工監理を請ける設計者に対しても、要望を的確に捉え、その要望をどれだけ汲み取り具現化してあげられるか」。
例えば施主のなかには「何かいいものにしてもらいたい」という漠然とした要望を持っている人も多い。「コミュニケーションを通じてその要望を確認し、いかにこちらが近いものを目の前に現してみせるか」(大内さん)。
例えば施主のなかには「何かいいものにしてもらいたい」という漠然とした要望を持っている人も多い。「コミュニケーションを通じてその要望を確認し、いかにこちらが近いものを目の前に現してみせるか」(大内さん)。
 施主の要望の汲み取りがしっかりできているか。大内さんがそのバロメーターとしているのが施主との対話のなかから感じるテンション(高揚感)だ。「お客さんのテンションが最高潮に達するのは上棟式。大金をかけ、時間をかけて練り上げた家のプランが立体的になって目の前に現れるのだからテンションがあがるのも当然。そのテンションを、竣工・引き渡しまでどうやって維持出来るかが勝負」という。
施主の要望の汲み取りがしっかりできているか。大内さんがそのバロメーターとしているのが施主との対話のなかから感じるテンション(高揚感)だ。「お客さんのテンションが最高潮に達するのは上棟式。大金をかけ、時間をかけて練り上げた家のプランが立体的になって目の前に現れるのだからテンションがあがるのも当然。そのテンションを、竣工・引き渡しまでどうやって維持出来るかが勝負」という。要望を汲み取る難しさが大きいほど、完成したときに施主や設計者に与えられる満足感も大きい。そして与えることができた満足感は、自らの仕事の達成感として還元され、新しい創造のエネルギーとなる。「引き渡しをして、施主や設計者の方々からありがとうと言われたり、あなたに頼んでよかったといわれると、やってよかったなと思える」(大内さん)。
「顧客の満足」と「自身の達成感」という同社の2つの根幹を支える「要望を汲み取る」という技量。この技量の高い質を維持していくために、大内さんは「形にしていくことが楽しくなければできない」ときっぱり答える。
大内さんは新人時代の地場ゼネコンで経験した縦割り分業的な建築への違和感を今でも思い出す。
「サラリーマン時代は形をつくることが苦痛で仕方なかった」。
会社遍歴はそうした違和感から脱却し、大内さんなりの納得を求めた足跡でもある。独立した今では、設計者との共同作業を「できていくのが楽しくてしょうがない」と充実感を味わっている。